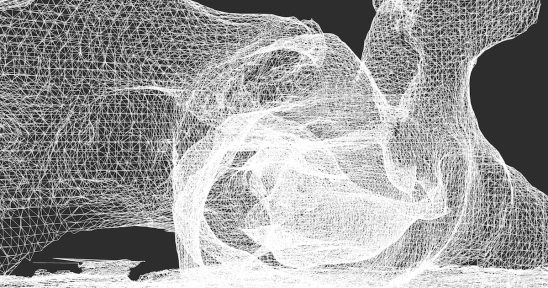国産広葉樹をもっと使いやすく。短期乾燥材の体験・相談ツアー

ものづくりは、少し前まで森にあった木で
昨年より飛騨市では、独自の広葉樹サプライチェーン構築を目指す連携組織「飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアム」が、木材の短期乾燥技術を確立するプロジェクトを進めています。通常、広葉樹材の製品化(製材品)には1年以上を要し、その過程で最も時間がかかるのが天然乾燥です。このプロジェクトで確立を目指すのは、天然乾燥を省略しても品質が維持できる乾燥技術。様々な角度で試験を重ね、製材したばかりの未乾燥材を最短30日〜40日で乾燥させることを実現しています。
このツアーでは、短期乾燥プロジェクトが目指すもの、そして乾燥実験で生産された乾燥材やそれを使用した空間を紹介。原木購入から乾燥材提供までのフローの説明や、購入・製作の相談会も実施します。
こんな方におすすめ
- トレーサビリティが確保された広葉樹をよりスピーディーに仕入れたい方
- 木製品の試作や開発サイクルを早めたい方
- ものづくりのマテリアルとして、新たに広葉樹を検討したい方
- 短期乾燥材の購入や、それを使った製作について相談したい方
About the event イベント詳細
開催情報
| 開催日 | 2022年10月7日(金)終了、10月19日(水)終了、11月3日(木•祝)定員に達したため受付終了 |
|---|---|
| 会場 | 岐阜県飛騨市古川町(集合:飛騨市役所) |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | 1回5組(1組2名まで) |
| 申込方法 | 本イベントは定員に達したため受付を終了致しました |
| 申込締切 | 各回、開催日の2日前12:00まで |
プログラム
| 13:00-14:30 | 「広葉樹のまちづくり」の概要説明・短期乾燥PJの説明(飛騨市役所会議室) |
|---|---|
| 15:00-16:00 | 土場・製材所・乾燥機の見学、原木購入・製材・制作依頼フローの説明(柳木材土場) |
| 16:00-16:30 | 広葉樹短期乾燥材の内装材・家具制作事例見学(ヒダクマ森の端オフィス) |
| 16:30-17:30 | 振り返りと相談会 |
| ※オプション | オプションプログラムとして、ご希望の方には本年度伐採予定の森を、ツアー日の前日または翌日にご案内いたします。ご希望の場合は、申し込み時にその旨ご記載ください。 |
■ 主催:飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアム
■ 企画・運営:株式会社飛騨の森でクマは踊る
※このツアーは、飛騨市広葉樹活用推進コンソーシアムからの委託を受け株式会社飛騨の森でクマは踊るが企画・運営を行うものです。
■ お問い合わせ:ヒダクマイベント事務局
E-mail: pr@hidakuma.com Tel: 0577-57-7686
Values
自らトレースできるプロセス
飛騨地域の森を出自とする原木を、域内の土場、製材所、乾燥施設で製品化し、お届けします。製材所や乾燥施設は本ツアーで紹介するほか、要望に応じて森を案内することも可能。プロセスの透明性が確保されているだけでなく、それを自らトレースできるマテリアルとして広葉樹を提供します。
より上流から選べるマテリアル
現状の広葉樹の流通構造の中で、作り手の方々は仕分けられ選別された在庫の中から、材料を選ぶしかありません。しかし、流通からこぼれ落ちる原木の中には、作り手のニーズにマッチしたものが含まれています。原木を選び製材をオーダーできる短期乾燥プロジェクトの取り組みにおいて、広葉樹はより上流から選ぶことのできるマテリアルです。
商品開発のサイクルを早める
商品開発に素早く着手したい、試作・検証サイクルを早く回したい方にも、短期乾燥材はおすすめです。短期乾燥で仕様を固め、本製作に向けては通常の天然乾燥で材料量を確保することができます。マテリアルを良材に限らない、新たな樹種を使用したいといったチャレンジングなプロジェクトに最適です。
その他、短期乾燥材の特徴やメリットについてはこちらの関連記事をご覧ください。
関連記事:森との距離を近づける、乾燥技術の確立へ
Navigators

及川幹|Motoki Oikawa
広葉樹活用コンシェルジュ
大阪大学文化人類学専攻を卒業後、西垣林業(株)に入社。製材工場にて営業や入出荷管理を経験後、新工場の立ち上げのため豊田に異動。生産管理や現場作業を経験したのち、2020年4月より飛騨市地域おこし協力隊、広葉樹活用コンシェルジュに着任。需要と供給のマッチングを通した、vernacularな木材流通の構築を目指す。短期乾燥プロジェクトの実務も兼任。

飛騨の森でクマは踊る|Hidakuma
岐阜県飛騨市を拠点に、地域に広がる「広葉樹の森」の活用・循環・価値創造に取り組む会社。
木工職人、建築家・デザイナーなど地域内外のパートナーとともに、ユニークなアイデアで、プロダクトから建築空間まで幅広い設計製作のプロジェクトを実践。また、宿泊可能なものづくりカフェ「FabCafe Hida」を運営し、森の恵みを楽しむイベントや、森の循環に触れるツアープログラムを提供している。